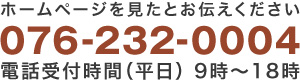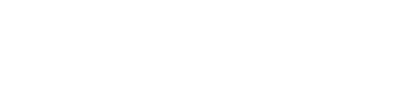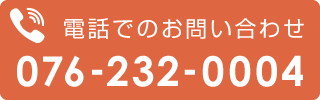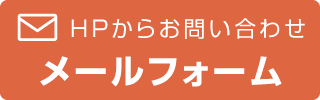Author Archive
借金は財産分与の対象になる?
「借金も財産分与の対象になるのでしょうか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
確かに借金が財産分与の対象になる可能性はありますが、必ずしもそうとは限りません。
法律上「マイナスの財産分与」はしないからです。相手から「借金を半分負担するように」と言われても、基本的に応じる必要はありません。
今回は借金が財産分与の対象になるのか、金沢の弁護士が解説します。
夫から「離婚するなら借金やローンも財産分与する」といわれてお困りの方はぜひ参考にしてみてください。
1.財産分与とは
そもそも離婚時の財産分与とはどういった制度なのか、簡単に確認しましょう。
財産分与は、離婚時に夫婦の共有財産を清算するための制度です。婚姻時、夫婦が協力してつみたてた財産の多くは「共有状態」になります。ただ離婚後は共有のままにしておけないので、財産分与によって分配するのです。これを「清算的財産分与」といいます。
清算的財産分与では、基本的に夫婦が財産を2分の1ずつに分け合います。ただし話し合いによって両者が納得すれば、2分の1以外の割合で分けてもかまいません。
財産分与の対象資産
一般的に財産分与の対象になることの多いのは以下のような財産です。
- 現金、預金
- 保険(積立式のもの。生命保険、火災保険、学資保険など)
- 不動産
- 車
- 株式や投資信託、国債など
- 価値のある動産類
- 退職金
夫が今後10年以内に退職する予定があって退職金が支給される可能性が高い場合、退職金(見込額)も財産分与対象になる可能性があります。
夫名義の財産だけではなく妻名義の財産も分与対象になるので、財産分与の話し合いの際にはお互いが財産を開示し合って公平に分け合いましょう。
2.財産分与の対象になる借金
借金については、財産分与の対象になるものとならないものがあります。
以下ではまず、財産分与の対象になる借金をみてみましょう。
2-1.生活費のための借金
生活費のための借金であれば、財産分与の対象になる可能性があります。
たとえば以下のような借金やローンです。
- 生活費が足りずに利用したカードローンやクレジットカードなどの残債
- 家族で使う車のローン
- 家族で住むための家の住宅ローン
- 家族で使うパソコンなどの購入費用の分割払いの残債
2-2.借金の清算方法、計算例
借金を財産分与の対象として清算する場合、以下のように計算します。
STEP1 プラスの資産からマイナスの借金を引き算する
まずは夫婦のプラス資産からマイナスの負債を引き算します。その数字が財産分与対象額です。
たとえば800万円の資産があり、生活費のための借り入れが200万円ある場合には800万円-200万円=600万円が正味の財産分与対象額となります。
STEP2 夫婦で2分の1に分ける
正味の財産分与対象額を夫婦で2分の1ずつに分け合います。
たとえば上記の事例なら正味の財産分与額が600万円なので、お互いの取得分は300万円ずつです。
借金の名義が夫であれば、夫は500万円分の資産を受け取って妻へ300万円を支払います。借金の名義が妻であれば、妻が500万円を受け取って夫へ300万円を支払って清算します。
2-3.マイナスの財産分与は行わない
借金の財産分与を行う際「マイナスの財産分与はしない」ので注意が必要です。
マイナスの財産分与とは、プラスの資産から負債を引いたときにマイナスになるケースでの借金の分配です。
たとえばプラスの資産が300万円あって借金が500万円ある場合、差し引きすると-200万円となってしまいます。
この場合、夫と妻が100万円ずつ負債を負担する、といった結論にはなりません。
財産分与はあくまでプラス資産がある場合に行うものです。
夫から「うちの家計はマイナスだったから、離婚後はローンを半額払うように」などといわれても必ずしも応じる必要はありません。
2-4.債権者には対抗できない
財産が全体でマイナスになってしまう場合はもちろん、プラスになる場合であっても知っておくべきことがあります。
それは「借金の財産分与は債権者には主張できない」ことです。
たとえば資産が800万円、夫名義の負債が200万円あって夫婦が300万円ずつの資産を受け取るケースにおいて、借金を離婚後に払い続けるのは夫だけです。妻が100万円を支払う義務はありません。債権者から請求される心配も不要です。
3.財産分与の対象にならない借金
以下のような借金は財産分与の対象になりません。
3-1.個人的な借金
夫婦どちらかの個人的な借金は財産分与から外れます。典型的には以下のようなものです。
- ギャンブルのための借金
- 個人的な投資の失敗の穴埋めのための借金
- 事業に失敗した分の借金
- 浪費のための借金
3-2.相手に伝えていなかった借金について
「相手に秘密の借金」であっても、それが生活費のための借り入れなら財産分与対象にできる可能性があります。相手から「聞いていなかった借金なので差し引きはしない」と言われても、あきらめずに弁護士まで相談してみてください。
4.住宅ローンがある場合の財産分与
住宅ローンがある場合、アンダーローンかオーバーローンかを調べなければなりません。
アンダーローンなら財産分与対象になりますが、オーバーローン物件は財産分与対象から外れます。
ただオーバーローンであっても、離婚後にどちらが住むのか、任意売却を行うのかなど決めなければならないケースが多数あります。
迷われたときには弁護士までご相談ください。
なお住宅ローンがある場合の財産分与についてはこちらの記事で詳しく解説しているので、ご参照ください。
8の記事にリンク
5.財産分与を有利に進める方法
財産分与を有利に進めるには、以下のように対応しましょう。
5-1.財産隠しを防止する
まずは相手による財産隠しを防止しなければなりません。
相手名義の預貯金や保険、株式などについてはすべて提示させましょう。
相手が隠す場合、調査が必要になるケースもあります。
弁護士であれば職権で調べられる可能性があるので、迷ったときにはご相談ください。
5-2.正確に評価する
財産が明らかになったら、正確に評価しなければなりません。不当に低く評価されると受け取れる財産額が低くなってしまう可能性があります。
特に不動産などの価値が変動したり評価方法がいくつかあったりする財産には注意が必要です。
評価方法がわからない場合にも弁護士がアドバイスしますので、お気軽にご相談ください。
5-3.法律知識を取得しておく
財産分与で不利にならないためには、法律の正確な知識が必要です。
知識がないまま話し合いに臨むのは、武器を持たずに戦いに挑むのと同じように無謀といえます。
事前に本を読んだり弁護士に相談したりして、必要な知識を頭に入れておきましょう。
5-4.弁護士に依頼する
財産分与を有利に進めるためには、弁護士に依頼するようおすすめします。弁護士であれば法律知識を駆使して依頼者のために相手と交渉できますし、相手の財産隠しも防ぎやすくなります。
以下では、財産分与に関する知識を解説しておりますので、ご覧ください。
金沢のあさひ法律事務所では女性の離婚相談に力を入れていますので、借金の財産分与などの問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。
石川県(金沢市・小松市・七尾市・白山市・野々市市など)をはじめ、富山県・福井県の離婚や慰謝料に関するご相談に幅広く対応しています。
これまで多くの方のお話を伺い、それぞれの事情に合わせた解決を一緒に考えてきました。つらい気持ちを抱えたままにならないよう、気軽に話せる場所としてお役に立てればと思っています。
初回相談は無料、事前予約で夜間や休日の対応も可能です。相談内容は厳守し、ご不安な気持ちに寄り添いながら、納得のいく解決を一緒に目指します。
※初回無料相談は、事務所で面談して相談する場合に限らせていただいております。電話での初回無料相談は行っておりませんので、ご注意をお願いいたします。
財産分与の資料の集め方や保管方法について
「財産分与の資料はどのようにして集めれば良いのでしょうか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
離婚の交渉を始める前に財産分与資料を適切に集めておかないと、後の離婚協議で不利になってしまうリスクも発生するので要注意です。
今回は離婚を有利に進めるための財産分与の資料の集め方や保管方法について、弁護士がお伝えします。
これから離婚を進めようと考えている方はぜひ参考にしてみてください。
財産分与では資料集めが重要
一般的に有利に離婚を進めるには、財産分与が非常に重要なポイントとなります。
財産分与とは、夫婦が婚姻中につみたてた資産を離婚時に分け合うことをいいます。
できるだけ多くの財産分与を受けられれば、離婚後の生活も安心できるでしょう。
財産分与を多く受け取るには、相手による財産隠しを防止する必要があります。隠されてしまったら、その財産は「ないのと同じ」なので、財産分与対象にできません。
相手による財産隠しを防止するために、事前の資料集め(証拠集め)が重要です。
こちらがしっかり資料を持っていたら、相手も「そんな財産はない」などと弁解ができなくなるものです。
離婚後に後悔しないように、事前にしっかり相手名義財産の資料を収集しましょう。
財産分与の資料集めをすべきタイミング
離婚の話し合いが始まってしまったら、相手は財産を隠してしまう可能性があります。
協議離婚の交渉を始める前に、しっかり財産関連資料を集めて手元に保有しておきましょう。
財産分与資料の集め方
一般的に財産分与資料は、以下のような方法で集めます。
財産の種類ごとにみてみましょう。
預貯金
預貯金については以下のような資料が必要です。
- 通帳の原本あるいはコピー、取引履歴
相手名義の通帳を発見したら全ページのコピーをとりましょう。
取引明細書がある場合にはプリントアウトしたりコピーをとったりしておいたりしてください。
社内積立、共済貯金
会社で社内積立している場合や公務員の共済貯金がある場合には、以下のような資料を集めましょう。
- 相手の給与明細書
給料から積立貯金が天引きされている事実がわかります。
- 社内積立や共済貯金に関する連絡書
連絡書にその当時の残高などが書かれているケースがあります。
不動産
自宅などの不動産については、以下の資料を集めてください。
- 不動産の全部事項証明書
法務局へ申請して取得します。
- 固定資産評価証明書
不動産がある場所の市町村役場へ申請して取得します。
- 不動産会社の査定書
任意の不動産会社で評価額を査定してもらい、査定書を出してもらいましょう。
いくつかの不動産会社へ依頼を出して、もっとも有利になる金額を出してくれた会社の査定書を残しておくのがおすすめです。
- 金銭消費貸借契約書やコピー
住宅ローンが残っている場合、金融機関との金銭消費貸借契約書の原本やコピーを用意しましょう。
- 保証委託契約書やコピー
住宅ローンが残っている場合には保証委託契約書についても原本やコピーを手元に残しましょう。
- 残ローンの償還予定表やコピー
残ローンの償還予定表についても原本あるいはコピーを用意しましょう。
車
- 車検証のコピー
車の場合、車検証のコピーを取りましょう。
- 査定書
車の価値を知るため、中古車業者などへ依頼して査定書を出してもらいましょう。
保険(積立式のもの)
- 保険証券や証券番号のわかるもの
証券が交付されている場合、保険証券のコピーを用意しましょう。
証券が交付されていない場合、保険会社からの通知書やネット上の画面をプリントアウトしたものなどを入手してください。
- 通知書などの解約返戻金がわかる書類
保険会社からの通知書などに解約返戻金が書いてある可能性があります。
1年に1回程度届く「保険内容のお知らせ」書類を探してみてください。
- 自分名義の保険については解約返戻金証明書
自分が契約者となっている保険についても財産分与対象になるので解約返戻金額を確認しておくべきです。保険会社へ解約返戻金の証明書を請求して保管しておきましょう。
株式などの有価証券類、投資信託など
株式などの有価証券類や投資信託などについては、以下のような資料を集めましょう。
- 証券会社からの通知書
月に1回や年に1回など、証券会社から契約状況についての通知書や確定申告用の書類が届くケースがあります。そういったものについてはコピーを取って保管しましょう。
- 株主通信や配当金についてのお知らせなど
年に2回程度、株主総会の招集通知、株主通信、配当金についてのお知らせ書類などが届きます。コピーを取って保管しましょう。
- 取引内容がわかる資料
証券会社との取引状況画面をプリントアウトしたものやスマホ画面を写真撮影したものなど、取引内容がわかる資料を残しましょう。
財産分与資料の保管方法
財産分与の資料は、原本またはコピーの形で保管します。
ほとんどのものはコピーでかまいません。原本が必要な際には相手に提示させれば良いからです。
ただし相手による使い込みが心配な場合、原本を預かるべきケースもあります。
また資料については自分で保管しなければなりません。
相手に見つからないように、自宅内で鍵が掛かる場所や貸金庫内などに入れておくと良いでしょう。弁護士に対応を依頼していれば、弁護士事務所に預けられるので安心です。
自分で資料を集めるのが難しい場合には弁護士へ依頼する
財産分与の資料集めは簡単ではありません。
集めるべき資料の内容も状況によって異なります。
また自分で探すには限界があります。個人情報の問題があり、たとえ夫婦であっても契約内容の開示に応じてくれない機関や会社が多いためです。
たとえば金融機関や保険会社、証券会社がわかっても、取引内容を開示してもらうのは困難です。多くは断られてしまうでしょう。そうこうしている間に相手方が財産隠ししてしまうかもしれません。
そんなときには弁護士へ対応を相談しましょう。
弁護士であれば、23条照会という方法によって相手の隠し財産を調べられる可能性があります。それでも開示してもらえない場合、調停や訴訟を申し立てれば裁判所から職権調査してもらえるケースがあります。
調査せずにあきらめてしまったらもらえる財産が減ってしまうリスクがあるので、まずは弁護士に状況を伝えて相談してみてください。
離婚問題を相談するならあさひ法律事務所へお気軽に
離婚問題を相談するなら、できるだけ離婚に力を入れている弁護士に相談すべきです。
普段から離婚案件を多く扱っている事務所であれば、財産調査もスムーズに進めてもらいやすいでしょう。
以下では、財産分与に関する記事を書いておりますので、ご覧ください。
金沢のあさひ法律事務所では女性側の離婚案件に積極的に取り組んでおり、財産分与に関する対応実績も多数あります。これから財産資料を集めたい方、資料が足りているか不安な方、離婚交渉を有利に進めたい方は、お気軽にご相談ください。
石川県(金沢市・小松市・七尾市・白山市・野々市市など)をはじめ、富山県・福井県の離婚や慰謝料に関するご相談に幅広く対応しています。
これまで多くの方のお話を伺い、それぞれの事情に合わせた解決を一緒に考えてきました。つらい気持ちを抱えたままにならないよう、気軽に話せる場所としてお役に立てればと思っています。
初回相談は無料、事前予約で夜間や休日の対応も可能です。相談内容は厳守し、ご不安な気持ちに寄り添いながら、納得のいく解決を一緒に目指します。
※初回無料相談は、事務所で面談して相談する場合に限らせていただいております。電話での初回無料相談は行っておりませんので、ご注意をお願いいたします。
住宅ローンが残っている場合の財産分与方法
「住宅ローンが残っている場合、どうやって家の財産分与をしたら良いのでしょうか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
住宅ローンが残っている場合、オーバーローンかアンダーローンかによっても対処方法が変わってきます。夫と妻、どちらかが家に住み続けるのか、あるいはどちらも住みたくないのかによっても対応が異なります。
今回は住宅ローンが残っている場合の財産分与方法を弁護士が解説しますので、離婚を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
アンダーローンかオーバーローンか調べる
住宅ローンの残った家を財産分与する際には、まずは「アンダーローン」か「オーバーローン」かを調べなければなりません。
アンダーローンとは
アンダーローンとは、ローン残額が家の売却価額より低い状態です。つまり家を売ればローンを完済できる状態をアンダーローンといいます。
オーバーローンとは
オーバーローンとは、ローン残額が家の売却価額より高い状態です。家を売ってもローンを完済できず、残債が残ってしまうとオーバーローンとなります。
アンダーローンかオーバーローンか調べる方法
アンダーローンかオーバーローンか調べたい場合、まずは家のローン残高を確認しましょう。金融機関から交付された返済予定表をみれば、現在残高を把握できます。
家の予想売却価額は不動産会社へ査定を依頼すれば出してもらえます。複数社に簡易査定を依頼して平均値をとるとより正確な値を出せるでしょう。
これら2つの数字が出たら、家の予想売却価額から残ローンを差し引きます。その数字がプラスならアンダーローン、マイナスならオーバーローン状態です。
アンダーローンの場合
アンダーローンの場合、家は財産分与の対象になります。ただし家の価額から残ローンを引いた金額が財産分与対象の価値です。
たとえば家の予想売却価額が1500万円、残ローンが700万円の場合には、財産分与対象額は800万円となります。
この場合、夫婦それぞれの財産分与取得分は400万円です。
たとえば夫が家を取得するなら妻へ代償金400万円を払う必要があり、妻が家を取得するなら夫へ400万円を払って清算するのが基本の対応となります。
なお家を取得する側と家の名義人が一致しない場合には、基本的に名義を揃える必要があります。そうでないと、離婚後に相手が住宅ローンを払わなくなって家が競売にかかる危険が生じてしまいます。
オーバーローンの場合
オーバーローンの場合には、家は財産分与対象から外れます。残ローンが上回る以上、家に価値はないと考えられるためです。ローンについては名義人が離婚後も払っていくことになります。
ただし実際には家をどのように処分するのか、どちらかが住み続けるのかどうかなどを決めなければなりません。名義人が住むなら問題ありませんが、名義人でない方が住むなら家やローンの名義変更をすべきです。
家とローンの名義変更をする方法
家の名義を変更するには、ローン名義も一緒に変えなければなりません。そのためには以下の2種類の方法があります。
- 新たな名義人が別の金融機関でローンを組んで借り換える
家を取得する側が別の金融機関でローン審査に通るなら、借り換えをするのが簡便でしょう。
- 現在の金融機関と相談して名義変更に応じてもらう
借り換えができない場合、現在の金融機関に相談して名義変更に応じてもらう必要があります。ただし新たな担保を要求されるケースなどもあり、必ずしも交渉がうまくいくとは限りません。
どちらかが頭金を出している場合の清算方法
妻側か夫側か、どちらかが頭金を出している場合には以下のように財産分与額を計算します。
頭金の割合を算定する
まずは家の価値のうち、頭金の割合を計算しましょう。
たとえば2000万円の家で妻側の両親が500万円の頭金を出している場合、妻側の頭金の割合は4分の1です。
現在価値に置き換える
次に頭金の割合を現在価値に置き換えます。
たとえば現在の家の価値が1200万円となっている場合、妻側の頭金に関する権利は1200万円×4分の1=300万円となります。
2分の1ずつに分ける
現在価値を基準として、家を2分の1ずつに分けます。
たとえば上記のケースの場合、1200万円の家なので基本的には600万円ずつとなります。
頭金の価値を考慮して調整する
妻側には頭金としての300万円分の権利があるので、600万円に300万円を足して900万円分を受け取れます。夫の取得分は300万円です。
離婚後も夫が家に住む場合には、妻へ900万円を払って清算する必要があります。妻が取得するなら夫へ300万円の代償金を払います。
どちらかが家に住みたい場合
住宅ローンの残った家がある場合、夫か妻のどちらかが家に住みたいか、あるいは住みたくないのかによっても対応が変わってきます。
どちらかが離婚後も家に住み続けたい場合には、基本的に家を取得する側が相手へ代償金を払って清算しましょう。
また家の名義変更が必要となるケースも多々あります。金融機関と調整ができず家の名義変更ができない場合、相手の名義の家に住む結果となって立場が不安定になってしまいます。
たとえば夫が住宅ローンと所有権の名義人になっている状態で妻や子どもが家に住み続けると、将来夫がローンを支払わなくなったときに家が競売にかかってしまいます。
妻と子どもは家に住めなくなるので、賃貸住宅などを探さねばなりません。
こういったリスクを考えると、自分名義ではない家に住むのはリスクが高いといえるでしょう。名義変更ができないのに家に住み続ける選択は、おすすめではありません。
どちらも家に住みたくない場合
どちらも家に住みたくない場合や代償金を払えない場合、名義変更できない場合などには、家を売却する方法をおすすめします。
アンダーローンの場合だけではなく、オーバーローン物件であっても家の売却は可能です。
離婚時に家を売っておけば、後に競売になる可能性もなく、名義変更の手間もかかりません。ただしオーバーローン状態の場合、名義人であっても金融機関に無断では家を売れません。「任意売却」といって金融機関の許可が必要となるので、まずはローン借入先の金融機関へ相談してみましょう。
アンダーローンの場合
アンダーローンの場合、家を売ると手元にいくらかのお金が残ります。
基本的には手残り分(売却価額から経費を引いた金額)を夫との間で2分の1ずつに分けると良いでしょう。ただしどちらかが家の頭金を出していたら、その分は考慮する必要があります。
オーバーローンの場合
オーバーローンの場合、家を売っても手元にお金が残らず、ローンが残ってしまいます。
ローンについては名義人が払っていくことになります。
連帯保証や連帯債務のリスク
家やローンの名義人になっていなくても、夫のローンの連帯保証人や連帯債務者となっている場合には注意が必要です。この場合、名義を外しておかないと、離婚後に残債を請求されてしまうリスクがあります。
夫に借り換えてもらうか金融機関と相談をするかして、保証人や連帯債務の名義を外しておきましょう。
財産分与でお悩みなら、あさひ法律事務所へ
石川・富山・福井で弁護活動を行う金沢のあさひ法律事務所では離婚案件に積極的に取り組んでいます。住宅ローンと家の財産分与で迷われた際にはお気軽にご相談ください。
財産分与については次の記事で解説していますので、ご覧ください。
石川県(金沢市・小松市・七尾市・白山市・野々市市など)をはじめ、富山県・福井県の離婚や慰謝料に関するご相談に幅広く対応しています。
これまで多くの方のお話を伺い、それぞれの事情に合わせた解決を一緒に考えてきました。つらい気持ちを抱えたままにならないよう、気軽に話せる場所としてお役に立てればと思っています。
初回相談は無料、事前予約で夜間や休日の対応も可能です。相談内容は厳守し、ご不安な気持ちに寄り添いながら、納得のいく解決を一緒に目指します。
※初回無料相談は、事務所で面談して相談する場合に限らせていただいております。電話での初回無料相談は行っておりませんので、ご注意をお願いいたします。
再婚をすると養育費が減額される?
「再婚すると養育費を減額されるのでしょうか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
確かに再婚して養育費が減ってしまうケースもありますが、必ずもそうとは限りません。
再婚と養育費との間には直接の関係はなく「養子縁組」するかどうかが問題となります。
今回は再婚したら養育費を減額されるのがどういったケースなのか、子どもと再婚相手を養子縁組させるべきかどうかを弁護士が解説します。
離婚後養育費を受け取っていて、再婚を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
再婚しても養育費は減額されない
離婚して親権者となると、別居親へ養育費を請求できるので、元夫から継続して受け取っている方も多いでしょう。
そんなとき、別の人と再婚したら養育費を減額されるのでしょうか?
実際に再婚したことを別居親(元夫)に知られると「これからは再婚相手に養ってもらえばいいので養育費は払わない」などと言われてしまう困ってしまう方が少なくありません。
しかし、同居親が再婚したからといって別居親における養育費の支払義務はなくなりません。減額されることもなく、これまでとおり支払いを受けられます。
再婚を相手に知られて養育費を払ってもらえなくなったら、あきらめずにこれまでとおり請求をしましょう。
養子縁組すると養育費をもらえなくなる
ただし再婚して相手に養育費を請求できなくなるケースもあります。それは、再婚相手と子どもを「養子縁組」した場合です。
養子縁組とは
養子縁組とは、もともと親子ではなかった人の間に法律上の親子関係を作り出す手続きです。
前夫との間の子どもと再婚相手には、もともと親族関係はありません。
ただし養子縁組すると、前夫との間の子どもと再婚相手が「親子」になるのです。
再婚相手は子どもの「父親(養親)」となるので、子どもを養育しなければなりません。
このように、養親が第一次的な養育義務を負うので、これまで養育費を負担していた実親の養育費支払義務がなくなります。
そこで再婚相手と養子縁組をすると、原則的に別居親へは養育費を請求できなくなる可能性が高くなるのです。
養子縁組しても養育費をもらえるケース
再婚相手と養子縁組をしても、養育費を請求できるケースがあります。
それは、再婚相手に十分な養育能力がない場合です。
たとえば再婚相手が障がい者ではたらけない場合、無職無収入で生活保護を受けている場合などには前夫である実親へ養育費を請求できると考えてよいでしょう。
また再婚相手に収入があっても子どもの養育に不十分な場合、前夫に不足分を請求できる可能性もあります。その場合、今までよりは養育費が減額されても、まったく請求できなくなるわけではありません。
再婚して養子縁組した場合に養育費を請求できるのか、いくら支払いを求められるのかについては個別の事案ごとの判断が必要です。迷われたときには弁護士までご相談ください。
養子縁組するメリット
確かに子どもと再婚相手を養子縁組させると養育費を請求できなくなったり減額されたりするデメリットがあります。
ただ以下のようなメリットもあるので、押さえておきましょう。
本当の親子になって家族を築きやすい
養子縁組をしない場合、子どもと再婚相手は「他人」のままです。
戸籍上も子どもは再婚相手の戸籍に入ることはなく、子どもの父親欄には前夫の名前しか記載されません。
養子縁組をすると、法律上は養親である再婚相手の子どもになります。戸籍も養親の戸籍に入れて「養親」と記載されます。
法律上は本当の親子になれるので、精神的な結合も強くなって家族を築きやすくなるでしょう。
遺産相続できる
法律上の親子になると、お互いに遺産相続権が発生します。
養子縁組をしなければ、再婚相手が死亡しても子どもは遺産を一切相続できません。再婚相手との子どもが生まれたときには格差ができてしまうでしょう。遺産相続トラブルが発生する可能性も高まります。
養子縁組をすると、再婚相手が死亡したときに連れ子も実子も同じように相続ができます。
今後一生再婚相手と添い遂げて連れ子を本当の子どものように育てていくなら、実子との間に遺産相続で不公平にならないよう、養子縁組をしておくべきといえるでしょう。
養子縁組するデメリット
一方、再婚相手と子どもを養子縁組させると以下のようなデメリットもあります。
養育費をもらえない可能性がある
まずは先に説明したように、養育費をもらえなくなる可能性が濃厚となる問題です。
ただ再婚したら再婚相手と一緒に家庭を築き、相手とは関わりを絶ちたい方も多いでしょう。
そういったご希望を持つ方にとって、相手に養育費をもらわなくなって縁を切ることはデメリットばかりとは限りません。
離婚したときの手続きが面倒
2つ目のデメリットは、再婚相手と離婚したときに発生する問題です。
再婚相手と離婚しても養子縁組は当然には解消されません。「離縁届」を作成して、役所へ提出する必要があります。
離縁届を提出しない限り、いつまでも子どもと再婚相手の親子関係が続いてしまうのは一定のデメリットといえるでしょう。
養子縁組する方法
再婚相手と子どもを養子縁組する場合には「縁組届」という書類を作成して役所へ提出する必要があります。再婚相手との婚姻届と同時でも良いですし、後から提出してもかまいません。
養子縁組するメリットとデメリットをふまえた上で養子縁組するかどうかを検討し、縁組をするなら再婚相手と話し合って縁組届を作成し届け出ましょう。
養育費が減額されるまでの流れ
再婚相手と子どもが養子縁組しても、その日から突然養育費が減額されるわけではありません。特に養育費の取り決めが公正証書や調停などで行われている場合、別途養育費の決め直しが必要です。前夫とよく話し合い、養育費を打ち切るのか減額するのかなどを決定しましょう。
あらたな条件が決まったら養育費の合意書を作成し直して、場合によっては公正証書も作成し直すべきです。新しい条件の養育費が決まったら、あらたな条件における養育費の支払いが始まります。
なお話し合っても養育費の打ち切りや減額について決まらない場合、相手から「養育費減額調停」を申し立てられる可能性があります。調停になると、調停委員が間に入って養育費を減額すべきか、どこまで減額するのかなどを話し合いによって定めます。養育費減額調停が不成立になると、裁判官が妥当な養育費の金額を定めて支払い命令を下します。
ただし相手から減額調停を申し立てられても必ずしも養育費が減額されるとは限りません。相手の言い分に納得できない場合には、弁護士へ相談をしましょう。
養育費のお悩みはあさひ法律事務所まで
金沢のあさひ法律事務所では、妻側の離婚案件に力を入れて取り組んでいます。
再婚を検討している方、養育費の支払いに不安のある方、養子縁組していないのに養育費を打ち切られてお困りの方など、お気軽にご相談ください。
また、養育費について次のような別記事でも開設しておりますので、ご覧になってくだだい。
養育費を払ってもらえない方必見!養育費を払って貰えないパターン別に対処法を解説
石川県(金沢市・小松市・七尾市・白山市・野々市市など)をはじめ、富山県・福井県の離婚や慰謝料に関するご相談に幅広く対応しています。
これまで多くの方のお話を伺い、それぞれの事情に合わせた解決を一緒に考えてきました。つらい気持ちを抱えたままにならないよう、気軽に話せる場所としてお役に立てればと思っています。
初回相談は無料、事前予約で夜間や休日の対応も可能です。相談内容は厳守し、ご不安な気持ちに寄り添いながら、納得のいく解決を一緒に目指します。
※初回無料相談は、事務所で面談して相談する場合に限らせていただいております。電話での初回無料相談は行っておりませんので、ご注意をお願いいたします。
損をしないように弁護士が解説!養育費の計算方法、取り決め方
養育費の金額を決めるときには、裁判所の定める相場に従うのが一般的です。
ただどのようにして養育費の金額を決めればよいのか、計算方法がわからない方も多いでしょう。
今回は養育費の計算方法や取り決め方をご説明します。
これから離婚する方、養育費を決め直したい方などはぜひ参考にしてみてください、
1.養育費の金額はいくらでも良いのか?
1-1.養育費とは
養育費とは、親が子どもの養育のために負担すべきお金です。
子どもを育てるにはさまざまな費用がかかります。ただ別居している親は自分で子どもを育てることがありません。そこで養育にかかる費用を送金しなければならないのです。それが養育費です。
離婚すると通常、親権者にならなかった方の親は子どもと一緒に暮らしません。そこで同居親に対し、子どもを育てるために養育費を払う義務を負います。
養育費の支払義務は「生活保持義務」という高いレベルの義務です。別居親は自分の生活レベルを落としてでも子どもに自分と同等の生活をさせなければなりません。
1-2.養育費はいくらでもかまわない
養育費の金額について「いくらにしなければならない」という絶対的なルールはありません。
基本的には当事者が納得していればいくらにしても良いのです。
一定の相場はありますが、当事者が納得していれば相場を無視した合意も有効です。
ただしそうはいっても支払う側はできるだけ支払額を抑えたいでしょうし、受け取る側はより多くの金額を求めるでしょう。
まったく基準がなければ合意できない可能性が高くなります。そこで裁判所では養育費の計算方法や標準的なケースにおける相場の金額を用意しています。
2.養育費の計算方法と算定表の読み方
裁判所の定める養育費の基準はどのようにして求めれば良いのでしょうか?以下で養育費の計算方法や簡易的な相場の求め方をご紹介します。
2-1.養育費の計算方法は複雑
裁判所の定める養育費の金額を計算するときには、支払う側と受け取る側の収入を基準にして「基礎収入率」という数値を定め、親や子どもにかかる生活費の指数なども用いて複雑な計算をします。
支払う側の収入が高い場合、基礎収入率を減らして調整する場合などもあります。
ただすべてのケースで個別的に養育費の計算をするのは大変なので、通常は「養育費の算定表」を用いて適切な養育費の計算を行います。
養育費の算定表とは、よくあるパターンごとに適正な養育費の金額をまとめた表です。
子どもの人数は1人~3人、年齢は14歳以下と15歳以上で参照すべき表が分かれるので、間違えないように正しい表を参照しましょう。
また養育費の算定表では、支払う側と受け取る側の収入額によって養育費の金額が変わります。基本的には支払う側の収入が高いと養育費の金額が上がり、受け取る側の収入が高いと養育費の金額は下がります。
さらに給与所得者と自営業者では「収入額」の見方が異なります。給与所得者の方は給与所得の欄に収入をあてはめ、自営業者の方は自営業者の方へと収入をあてはめましょう。
2-2.養育費の具体例
たとえば14歳以下の子どもが2人いて、支払う側(夫)の収入が年収500万円、受け取る側(妻)の収入が年収150万円の場合の養育費の金額をみてみましょう。
この場合、まずは「(表3)養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」を開きます。
そして、夫の年収500万円と妻の年収150万円をそれぞれ参照し、夫の収入からは右横方向へ、妻の収入からは上方向へと線を引っ張ります。そうしてぶつかる金額帯が妥当な養育費の金額となります。
この事例の場合、具体的には6~8万円が適正な養育費の金額と算定されるので、養育費を決めるときには、月額6~8万円として取り決めるのが良いでしょう。
3.子どもに特別にお金がかかる場合の養育費
裁判所の定める養育費の算定表は、あくまで子どもが健康で公立の学校に通う一般的なケースを想定しています。
子どもに重い障害や病気があって特別に医療費などがかかる場合、子どもが私学に行くので学費がかさむ場合などは想定されていません。
そういった事情がある場合、算定表で定める以上の金額を請求できる可能性が高いと考えましょう。
具体的にどのくらいの金額を請求できるのかは事案によって異なりますので、迷ったときには弁護士までご相談ください。
4.養育費を取り決める手順
養育費を取り決める手順をご説明します。
STEP1 まずは相手と話し合う
養育費の取り決めをするときには、まずは相手と話し合いましょう。
合意ができればすぐに養育費が決まります。離婚前であれば財産分与などの諸条件と一緒に話し合うのが良いですし、離婚後であれば養育費のみ話し合うと良いでしょう。
STEP2 養育費の合意書を作成する
養育費について取り決めができたら、養育費の支払いに関する合意書を作成します。
合意書には親同士が双方署名押印して日付を書き入れたものを2通作成し、お互いが1通ずつ所持しましょう。
STEP3 公正証書にする
養育費の合意書は公正証書にしておくようおすすめします。公正証書があれば、相手が滞納したときにすぐに差し押さえができて便利だからです。
養育費の合意書であっても離婚協議書に養育費を定めたケースであっても公正証書化は可能です。
STEP4 合意できない場合には離婚調停・養育費調停を申し立てる
相手と話し合っても養育費について合意できない場合、家庭裁判所で調停を申し立てましょう。
離婚前であれば「離婚調停(夫婦関係調整調停)」を申し立てれば、他の離婚条件とともに養育費についての話し合いもできます。
離婚後であれば「養育費調停」を申し立てましょう。調停委員が間に入って養育費についての話し合いを調整してくれます。
調停で合意できない場合
離婚調停の場合、合意できなければ「不成立」となって終わります。
養育費調停の場合、合意できなければ「審判」となり、審判官が妥当な養育費の金額を取り決めてくれます。
どちらの調停であっても有利に進めるには弁護士によるサポートが必要なので、迷われたときにはお早めにご相談ください。
5.養育費を弁護士に相談するメリット
養育費について困ったときに弁護士に相談すると以下のようなメリットがあります。
- 適正な養育費の金額がわかる
- 相手との交渉を任せられる
- 相手の主張より養育費が増額される可能性が高い
- 養育費の調停を任せられる
- 自分で対応しなくて良いのでストレスがかからない
- 離婚相談もできる、有利に離婚を進めやすくなる
養育費についてわからないことがあったり相手の言い分に疑問や不安があったりする場合、自己判断せずに弁護士へ相談しましょう。当事者の方が考える以上に養育費請求や離婚を有利に進められるケースが多数です。
養育費を払ってもらえない方必見!養育費を払って貰えないパターン別に対処法を解説
石川・富山・福井で弁護活動をする金沢のあさひ法律事務所では30代や40代の離婚を応援しています。
「子どもの養育費は必ず支払ってほしい」というお声もよくお聞きします。多くの方が「養育費をきちんと払ってもらえるのだろうか?」と不安を抱いているのです。
弁護士に任せれば養育費がきちんと支払われる可能性が大きく高まりますし、万一支払いを受けられないケースでは取り立ても可能です。
適正な金額を子どもが成人するまで受け取り続けるため、お気軽にご相談ください。
石川県(金沢市・小松市・七尾市・白山市・野々市市など)をはじめ、富山県・福井県の離婚や慰謝料に関するご相談に幅広く対応しています。
これまで多くの方のお話を伺い、それぞれの事情に合わせた解決を一緒に考えてきました。つらい気持ちを抱えたままにならないよう、気軽に話せる場所としてお役に立てればと思っています。
初回相談は無料、事前予約で夜間や休日の対応も可能です。相談内容は厳守し、ご不安な気持ちに寄り添いながら、納得のいく解決を一緒に目指します。
※初回無料相談は、事務所で面談して相談する場合に限らせていただいております。電話での初回無料相談は行っておりませんので、ご注意をお願いいたします。
モラハラに該当する行為や慰謝料の相場、離婚の進め方
「夫からモラハラを受けているかもしれません。離婚した方が良いのでしょうか?」
「モラハラとはどのような行為なのでしょうか?」
女性の方が、夫からモラハラ被害を受けるケースが少なくありません。
自分ではモラハラを受けていることに気づいていない方も多数おられます。
今回はモラハラに該当する行為や慰謝料の相場、離婚の進め方を弁護士が解説します。
モラハラとは
モラハラとは、いわゆる精神的な暴力です。
暴言を吐いたり物に八つ当たりをしたり子どもに悪口を吹き込んだり強い束縛をしたりなど、さまざまなタイプがあります。「モラルハラスメント」の略でモラハラとよばれます。
日本では、夫婦間でのモラハラが問題となるケースが多く、特に男性が女性に対してモラハラ被害をもたらす事例がよくみられます。
モラハラに該当する行為
モラハラ行為の典型的な行為を示します。
- 妻に暴言を吐く
- 妻本人や妻の実家の親族を侮辱する
- 妻の友人を馬鹿にする、侮辱する
- 妻を異常に束縛する
- 妻が働こうとすると反対する、嫌がらせをする
- 1日のスケジュールを決めてそのとおりにしないとキレる
- お金に細かい、妻に「家計を管理できない」といってなじってくる
- 自分の非を絶対に認めない
- 気に入らないことがあると何時間でも説教をする
- 突然無視し始めてまったく応答しなくなる
- ものに八つ当たりをする、壊す
- 子どもに妻の悪口を吹き込む(ママのようになってはいけないよ、などと告げる)
あてはまるものがあれば、あなたの夫もモラハラ男性かもしれません。
モラハラは離婚原因になる
モラハラ被害に遭っている場合でも、離婚に躊躇される方が少なくありません。そもそも夫がモラハラ行為を行っていることに気づいていなかったり、「自分が悪い」「自分だけが我慢していればいい」と考えてしまったりする傾向があるためです。「夫に離婚を要求しても受け入れられないだろう」とあきらめてしまう方も少なくありません。
しかしモラハラは違法行為であり、法律上も離婚原因になります。
訴訟で夫によるモラハラを立証できれば、夫が拒否しても裁判所が離婚を認めてくれます。慰謝料も請求できますし、夫が認めなくても財産分与や親権も獲得できる可能性があります。
夫に遠慮する必要はないので、辛い婚姻生活を営んでいるなら早めに弁護士へモラハラについて相談してみてください。
モラハラの慰謝料相場
モラハラ被害に遭っている場合、相手に慰謝料を請求できます。
モラハラの慰謝料の相場はだいたい50~300万円程度です。
モラハラの慰謝料増額事由
以下のような事情があれば慰謝料相場は高額になる傾向があります。
- モラハラを受けた期間が長い
- モラハラの内容が悪質
- 婚姻生活が長い
- 加害者が反省していない
- 被害者がうつ病などの精神病になった
- 未成年の子どもがいる
モラハラの証拠
夫からモラハラ被害を受けているなら、モラハラの証拠を集めておくべきです。
ただモラハラの場合、身体的な暴力ではないために証拠を集めにくい問題があります。
以下でどういったものが証拠として有効になるのか、集め方とともにみてみましょう。
LINEやメールの文章、やり取り
相手とのLINEやメールでのやり取りはモラハラの証拠になります。
相手から送られてきた暴言が書かれているLINEやメールは消さずに保存しましょう。プリントアウトできるものはプリントアウトしておく方法も有効です。
相手から渡された書面
1日のスケジュールや家計管理表など、モラハラ夫が書面を妻へ渡してくるケースが良くあります。
そういったものも相手による異常な束縛を証明する手段となるので、手元に残しておきましょう。
相手が壊したものの写真や動画
モラハラ夫があばれて壊したものの写真や動画も証拠になります。
相手が暴れているときの音声や録画
相手があばれたり暴言を吐いたりしている際の音声録音や録画データもモラハラの証拠になります。ICレコーダーやスマホなどで保存しましょう。
相手が発言している内容の音声や録画
相手が説教をしているときの録音やそのときの様子を写した動画などもモラハラの証拠になります。
詳細な日記
被害者自身がつけた日記であっても詳細なものであればモラハラの証拠になります。「モラハラ被害を受けた」などの抽象的な記載ではなく、なるべく詳細に書きましょう。
たとえば「友人の○○さんと会う約束をしていたのに外出を禁止されて会えなくなった」「お前は家計を管理できない、と怒鳴られた」などと記載します。
診断書
モラハラ被害を受けると、抑うつ状態となったりうつ病になったりして精神病になってしまう方も少なくありません。そんなときには相手に高額な慰謝料を請求できる可能性があるので、病院で診断書をもらっておきましょう。
モラハラに遭っている場合の離婚の進め方
夫からのモラハラ被害に遭っている場合の離婚の進め方は、モラハラの程度や夫婦の力関係によっても変わってきます。
以下で「自分で交渉できる場合」と「自分での交渉が難しい場合」に分けて対処方法を御伝えします。
自分で交渉できる場合
夫婦の力関係がさほど妻にとって不利でなくモラハラ夫が離婚に応じるなら、自分で交渉できる可能性があります。
その場合、まずは相手と話し合いをしましょう。離婚することについて了承をとった上で財産分与、慰謝料、親権や養育費などの取り決めを行います。
このとき、相手が強硬な態度に出たとしても、不当に折れてはなりません。
適正な条件で離婚しないと離婚後に後悔してしまいます。
合意できたら公正証書で離婚協議書を作成し、役所へ離婚届を提出しましょう。
自分で交渉できない場合
自分で交渉するのが難しい場合には、以下のように対応しましょう。
別居して調停を利用する
まずは相手と別居するようおすすめします。同居したままでは相手による支配下から抜けだせないためです。
別居したら、離婚調停を申し立てましょう。調停を利用すれば自分で直接話す必要がありません。生活費を払ってもらえないケースも多いので、その場合には婚姻費用分担調停も同時に申し立てましょう。
別居して弁護士を入れる
別居した後、調停ではなく弁護士を入れて直接交渉する方法も有効です。
弁護士を入れれば自分で対応する必要はありません。相手がモラハラ加害者であっても有利な条件を定められて慰謝料も請求できるケースが多数あります。
どうしても合意できない場合には弁護士へ離婚調停を依頼しましょう。
訴訟を起こす
調停が不成立になってしまったら、離婚訴訟を起こします。モラハラを立証できれば裁判所が離婚を認めてくれて、慰謝料の支払い命令も出してくれます。
財産分与や親権、養育費なども裁判所が決めてくれるので、モラハラ夫と話し合う必要はありません。
ただし訴訟に1人で取り組むのは極めて困難なので、弁護士へ依頼しましょう。
石川・富山・福井で弁護活動をする金沢のあさひ法律事務所はモラハラ被害に苦しむ女性の方へサポート体制を整えています。お困りの方はお気軽にご相談ください。
石川県(金沢市・小松市・七尾市・白山市・野々市市など)をはじめ、富山県・福井県の離婚や慰謝料に関するご相談に幅広く対応しています。
これまで多くの方のお話を伺い、それぞれの事情に合わせた解決を一緒に考えてきました。つらい気持ちを抱えたままにならないよう、気軽に話せる場所としてお役に立てればと思っています。
初回相談は無料、事前予約で夜間や休日の対応も可能です。相談内容は厳守し、ご不安な気持ちに寄り添いながら、納得のいく解決を一緒に目指します。
※初回無料相談は、事務所で面談して相談する場合に限らせていただいております。電話での初回無料相談は行っておりませんので、ご注意をお願いいたします。
養育費を払ってもらえない方必見!養育費を払って貰えないパターン別に対処法を解説
「離婚後、養育費を払ってもらっていないのですが、どうすれば良いでしょうか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
離婚して子どもを引き取ったら、別居親は子どもの養育費を負担しなければなりません。それにもかかわらず養育費を払わない別居親も多数存在するのが実情です。
今回は養育費を払ってもらえないときの対処方法を、パターン別に弁護士がお伝えします。
別居親には養育費の支払義務がある
子どもと離れて暮らす親は、子どもの養育費を払わねばなりません。
離れて暮らしていても、親子であることに変わりはないからです。親には子どもへの扶養義務があるので、子どもの生活費を負担する必要があります。
別居親が養育費を払わねばならない義務は「生活保持義務」という高いレベルの義務です。つまり自分の生活レベルを落としてでも子どもに自分と同等の生活をさせなければなりません。
養育費には、以下のような費用が含まれます。
- 衣食住の費用
- 学費、教育費
- 日用品費
- 交通費
- 交際費
- 雑費
ただし上記のような費用を個別的に計算して清算することは通常ありません。養育費は「月額の定額」として毎月一定日に支払われるのが一般的です。
養育費の金額
養育費の金額については、当事者同士が納得すればいくらであってもかまいません。
ただし裁判所が基準を定めているので、妥当な金額を決められないときにはこちらを参考にすると良いでしょう。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
支払い側の収入が高ければ養育費の金額が上がり、受け取る側の収入が高ければ養育費の金額が下がる計算方式です。また子どもの人数が増えたり年齢が15歳以上になったりすると養育費がかかるので、金額は上がります。
家賃が高い、ローンや借金がある、は減額事由にならない
養育費を払わない相手は、「家賃が高い」「住宅ローンを払っている」「借金の返済がある」などと理由をつけて養育費の支払いを拒否するケースが少なくありません。
しかしこういった理由は養育費を拒否する理由になりません。
相手の養育費支払義務は「生活保持義務」であり、自分と同等の生活をさせなければならないからです。
相手に収入がある限り、家賃や借金などの支払いがあっても算定表とおりの金額を請求できると考えましょう。
以下ではパターン別に、相手が養育費を払わないときの具体的な対処方法をご説明します。
養育費の取り決めをしていない場合
まずは相手へ請求する
離婚時にまったく養育費の取り決めをしていない場合、まずは相手へ養育費の支払いを請求しましょう。
相手が任意に支払うなら、養育費の支払いを受けられるようになります。
合意内容を公正証書にする
養育費について合意する際には口約束ではなく、必ず書面に合意内容をまとめましょう。
また養育費の合意書は「公正証書」にするようおすすめします。公正証書があれば、相手が後に約束を破って支払わないときにすぐに差し押さえができるからです。
相手が払わないなら養育費調停を申し立てる
相手に請求しても養育費を払わない場合には、家庭裁判所で養育費調停を申し立てましょう。
調停を申し立てると、調停委員会が間に入って養育費の取り決めを支援してくれます。
話し合いには調停委員が介在するので、相手と直接顔を合わせたり会話したりする必要はありません。
養育費の算定表をもとに調停案も示してもらえます。双方が合意すれば調停が成立し、養育費の支払いを受けられるようになります。
どうしても調停が成立しない場合、手続きは「養育費審判」となります。
審判では裁判官が妥当な養育費の金額を取り決めて、相手へ支払い命令を下してくれます。
養育費の合意書がある場合
離婚時に一応養育費の約束をして合意書がある場合、その合意書が公正証書か単なる一般的な書面かで対応が変わってきます。
公正証書の場合
離婚時に離婚公正証書で養育費を定めたり養育費に関する合意書を公正証書にしたりしている場合、すぐに相手の給料や預貯金などを差し押さえられます。差し押さえを強制執行といいます。
それ以外にも以下のような「債務名義」があれば、強制執行が可能です。
- 公正証書
- 調停調書
- 審判書
- 裁判上の和解調書
- 請求の認諾調書
- 判決書
強制執行するときには、債権者が相手方の資産を明らかにしなければなりません。勤務先がわかれば給料を差し押さえられます。
取引している金融機関名がわかれば預貯金を、保険会社がわかれば保険の解約返戻金を、取引している証券会社がわかれば株式や投資信託などを差し押さえできます。
相手の資産が不明な場合、裁判所の手続きを利用して調べられる可能性があります。
相手方本人に財産状況を報告させる手続きや、裁判所から勤務先や金融機関、不動産関係の情報照会する手続きも利用できる可能性があるので、詳細は弁護士までご相談ください。
一般的な書面による取り決めがある場合
養育費の取り決めを一般的な書面で行っていて公正証書がない場合には、直接の差し押さえができません。いったん養育費調停を申し立てる必要があります。調停や審判で養育費の支払いが決まったら、相手から支払いを受けられるようになるのが一般的な流れです。
養育費調停の申立方法
相手方が養育費を払わない場合、養育費調停を申し立てなければならないケースがあります。調停の申立方法を把握しておきましょう。
管轄の裁判所
管轄の裁判所は「相手の住所地を管轄する家庭裁判所」です。調停が始まったら、基本的には毎回出頭しなければなりません。ただし遠方の場合、ビデオリンク方式を利用して出頭回数を抑えられる可能性もあります。
必要書類
基本的な必要書類は以下のとおりです。
- 子どもの戸籍謄本
- 申立書
- 事情説明書
- 収入資料(給与明細書や源泉徴収票、確定申告書など)
費用
- 子ども1人について1200円の収入印紙
- 連絡用の郵便切手
上記を揃えて家庭裁判所へ提出しましょう。
養育費の請求を弁護士に依頼するメリット
相手にプレッシャーをかけて支払いに応じさせやすくなる
弁護士から相手へ養育費の請求通知を送ると、相手としてはプレッシャーを感じるものです。自分で請求しても無視されたケースでも、弁護士から連絡すると養育費が払われるケースが少なくありません。
適切な手続きを選択できる
養育費の請求に必要な手続きはパターンによって異なりときには大変複雑になります。弁護士がついていると状況に応じて適切な手続きを選択でき、スムーズに養育費の請求ができます。
手間のかかる裁判手続を任せられる
養育費を請求する際には、調停や差し押さえ、情報照会など手間のかかる手続きも行わねばなりません。弁護士に任せていれば自分で対応しなくて良いので、手間も時間も省けるメリットがあるといえるでしょう。
ストレスがかからない
支払いをしぶる相手に養育費の請求をするのは大変なストレスになるものです。調停が始まっても調停委員との対話を進めなければならず、やはりストレス要因となってしまう方が多数おられます。
弁護士に任せてしまえば自分で対応しなくてよいので気持ちも楽になるでしょう。
養育費については、次のような記事もご参照ください。
養育費を払ってもらえない方必見!養育費を払って貰えないパターン別に対処法を解説
石川・富山・福井で弁護活動をする金沢のあさひ法律事務所では離婚問題の解決に力を入れています。養育費を払ってもらえずお困りの方は、お気軽にご相談ください。
石川県(金沢市・小松市・七尾市・白山市・野々市市など)をはじめ、富山県・福井県の離婚や慰謝料に関するご相談に幅広く対応しています。
これまで多くの方のお話を伺い、それぞれの事情に合わせた解決を一緒に考えてきました。つらい気持ちを抱えたままにならないよう、気軽に話せる場所としてお役に立てればと思っています。
初回相談は無料、事前予約で夜間や休日の対応も可能です。相談内容は厳守し、ご不安な気持ちに寄り添いながら、納得のいく解決を一緒に目指します。
※初回無料相談は、事務所で面談して相談する場合に限らせていただいております。電話での初回無料相談は行っておりませんので、ご注意をお願いいたします。
元妻・元夫に面会交流させたくない!面会交流を拒否できるケースとは
「どういったケースで面会を拒否できるのでしょうか?」
「子どもを離婚した元夫に会わせたくありません」
こういったご相談をお受けするケースが多々あります。
離婚後、子どもと別居親との面会を巡ってトラブルになる事例は非常に多く、別居親から強硬に子供との面会を求められて困惑してしまう親権者の方がいらっしゃいます。
面会交流は拒否できないのが原則ですが、状況によっては拒否できる可能性もあります。今回は面会交流を拒絶できるケースや相手から無理な面会交流を要求された場合の対処方法を弁護士がお伝えします。
離婚後の面会についてお悩みの方がおられましたらぜひ参考にしてみてください。
面会交流とは
面会交流とは、子どもと別居親が会ったり電話やメールなどによって交流したりすることを意味します。
法律上、親子が離れて暮らしていても、「子どもと親は交流を続けるべき」と考えられています。
離婚すると単独親権しか認められないので子どもの親権者はどちらか一方となりますが、その状態でも子どもは親と会う権利が認められますし、親にも子どもと会う権利が認められるのです。
子どもが「両方の親から愛されている」という自覚を持って健全に成長してくためにも、面会交流は極めて重要な要素と考えられています。
民法でも、離婚する際には、基本的に面会交流に関する事項も定めておくべきと定められています(民法766条)。
離婚後の面会がスムーズに進まないパターン
面会交流は子どもにとっても別居親にとっても重要な権利です。しかし実際には離婚後の面会交流がスムーズに進まないケースも少なくありません。
別居親と同居親の意見が合わない
面会交流をスムーズに実施するには、同居親と別居親の協力が不可欠です。
しかし離婚した親同士のやり取りはうまくいかないケースも少なくありません。
別居親が「毎日会わせてほしい」「毎週末泊まらせるように」「祖父母にも会わせたい」などと主張するのに対し、同居親は拒否するので面会が実現できなくなってしまうパターンです。
同居親が再婚して面会を拒否する
子どもを育てている同居親が再婚すると、面会交流が難しくなってしまうケースがよくあります。再婚すると、同居親は「子どもを新しい家庭になじませたい」と考えるためです。
「そのためには、実親である別居親との関係を絶たねばならない」と考えてしまい、面会を拒否するようになります。
別居親は納得できないので、大きなトラブルにつながるパターンです。
別居親による面会交流の方法が不適切
別居親による面会交流の方法が不適切なためにトラブルとなる事例もよくあります。
たとえば別居親が時間にルーズで送り迎えの時間に遅れると、同居親は不安を感じるでしょう。別居親が同居親の悪口を吹き込んだり「一緒に暮らそう」などと誘って子どもを困らせたりするケースもあります。
こういった対応をすると、同居親が面会交流を拒否するようになって実施が難しくなってしまう可能性が高くなります。
面会交流は原則として実施しなければならない
別居親が強く面会を求めてきて同居親としては会わせたくない場合、面会交流を拒否してもかまわないのでしょうか?
冒頭でもご説明した通り、法律は面会交流を子どもにとっても親にとっても非常に重要な権利と考えています。よほどの障害事由があればともかく、多少の問題がある程度であれば面会交流を実施すべきというのが結論です。
たとえば以下のような理由で面会交流を拒むことはできません。
再婚したので子どもを新しい家庭になじませるため、相手と会わせたくない
相手が時間に遅れる
子どもが相手と会うとしばらく寂しがってぐずる、泣く
相手と面会させると、おねしょが復活した、学校や幼稚園で喧嘩をした
相手とは今後関わりたくない
子どもに実の父親を忘れさせたい
相手が勝手に子どもを祖父母と会わせていた
養育費をもらっていない
面会交流と養育費の関係
ときどき、「養育費をもらっていないので面会交流をさせない」と主張する方がおられます。
しかし養育費と面会交流は引き換えではありません。
相手には養育費を払う義務があり、同居親としては相手と子どもを会わせる義務があります。たとえ相手が養育費を払っていないとしても、面会はさせなければならないのが原則です。養育費を受け取っていないことは、面会交流を拒否する理由になりません。
面会交流を例外的に拒絶できるケースとは
以下のような場合、例外的に面会交流を拒否できる可能性が高いといえます。
相手が子どもを虐待する
相手が婚姻中に子どもを虐待していた、あるいは面会すると虐待する場合には面会交流を拒否できます。子どもに明白な危害を加えられるおそれがある以上、面会交流を実施すべきではありません。
相手が子どもを連れ去る可能性が高い
これまでの面会で相手が子どもを連れ去ったことがあるなど、連れ去りリスクが具体的で蓋然性が高い場合にも面会交流を拒否できる可能性があります。
ただし実際に連れ去られるリスクが高いことが必要で、単に同居親が「連れ去られるかもしれない」と心配しているだけであれば拒否は難しくなります。
相手が子どもを違法行為に巻き込むなど方法が著しく不適切
相手が子供との面会中に違法行為に巻き込むなど、面会の方法が著しく不適切な場合にも面会を拒否できます。
たとえば大麻草の栽培、オレオレ詐欺への加担、万引きをさせるなどの犯罪行為をさせたり援助交際させたりする場合などです。
相手が明らかに不合理な要求をしている
遠方に居住する別居親が毎日などの頻繁な面会を求め、交通費も全額負担するよう要求するなど非現実的で不合理な要求をする場合、そういった条件での面会交流に応じる必要はありません。ただし実現可能な方法による面会を検討していく必要はあるでしょう。
相手が無理な主張をする場合の対処方法
別居親が子どもの都合も聞かずに「毎日会わせてほしい」などと無理な主張をしてくるようであれば、家庭裁判所での面会交流調停を利用しましょう。
面会交流調停では、裁判所の調停委員会が両親の間に入って調整してくれるので、相手と直接話す必要はありません。調停案に双方が合意すれば、調停がまとまって面会に関するトラブルを解決できます。
どうしても意見が合わない場合、調停は不成立となって審判になります。審判では審判官が事案に応じて適切な面会交流の方法を定めます。
なお審判で決まった面会交流の方法は、守らねばなりません。審判を無視していると相手から「間接強制」として給料や預貯金などの差し押さえを受ける可能性もあるので、無視しないように注意しましょう。
面会交流の定め方については、以下の解説をご覧ください。
石川・富山・福井で弁護活動をする金沢のあさひ法律事務所は離婚問題に積極的に取り組んでいます。子どもと別居親との面会交流にお悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
石川県(金沢市・小松市・七尾市・白山市・野々市市など)をはじめ、富山県・福井県の離婚や慰謝料に関するご相談に幅広く対応しています。
これまで多くの方のお話を伺い、それぞれの事情に合わせた解決を一緒に考えてきました。つらい気持ちを抱えたままにならないよう、気軽に話せる場所としてお役に立てればと思っています。
初回相談は無料、事前予約で夜間や休日の対応も可能です。相談内容は厳守し、ご不安な気持ちに寄り添いながら、納得のいく解決を一緒に目指します。
※初回無料相談は、事務所で面談して相談する場合に限らせていただいております。電話での初回無料相談は行っておりませんので、ご注意をお願いいたします。
親権を望む方へ親権の判断基準と決めるまでの流れを解説します
「子どもの親権者はどのような基準で決定されるのでしょうか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
日本では婚姻中は夫婦の共同親権となりますが、離婚後は共同親権が認められていません。単独親権となるので、どちらの親が離婚後の親権者になるのかを決める必要があります。
両方の親が親権を希望すると、大きなトラブルになるケースも多々あります。親権を取得するため、法的な判断基準を押さえておきましょう。
今回は親権者の判断基準や決定するまでの流れを解説しますので、親権を取得したい方はぜひ参考にしてみてください。
親権者の判断基準
親権とは、子どもの財産を管理し、養育看護する権利です。
離婚後の親権者は母親か父親のどちらかになるので、離婚の際にはどちらの親が離婚後の親権者となるのかを決めなければなりません。
両者が争っている場合、裁判所は以下のような基準で親権者を判断します。
- これまでの養育実績が高い
- 現在の子どもとの関係が良好
- 離婚後、子どもの養育に労力や時間をかけられる
- 現状子どもと一緒に暮らしており、子どもが落ち着いて生活になじんでいる
- 子どもが愛着を持っている
- 心身共に健康
- 経済状態に問題がない
- 離婚後の面会交流に積極的
- 子どもが乳幼児の場合、母親が優先される
- 子どもが15歳以上になると子どもが親権者を選べる
上記のような親は親権者の判断で有利になりやすいといえるでしょう。
以下ではポイントとなる2点を示します。
子どもと一緒に過ごせる時間が長い
離婚後に親権を取得したければ、生活スケジュールにおいてなるべく子どもと一緒に過ごせる時間が長いと有利になります。
たとえば経済力がなくても子どもと一緒に過ごす時間を長く取れる母親は有利になるケースが多数です。生活保護を受けていても親権者になることは可能です。
一方、経済力があっても仕事に忙しい父親は親権争いで不利になりがちです。
相手から「経済力がないから親権者にはなれない」と言われても、あきらめる必要はありません。
別居している場合、子どもと一緒に暮らしている側が有利
離婚前に別居した場合、子どもと一緒に暮らしている親が有利になるケースが多数です。
「両親の離婚にともなって、何度も子どもの環境を変化させるのは好ましくない」という裁判所の判断があるためです。
親権を取得したいなら、別居の際に子どもと離れないようにしましょう。
たとえば夫と別居する際に「後で迎えに来る」と考えて子どもをおいて出ると、親権者になれないリスクが高まります。それどころか面会交流もまともにさせてもらえなくなる可能性もあるので、くれぐれも子どもとは離れないようにしましょう。
乳幼児の場合、母親が有利
子どもが0~3歳程度の乳幼児の場合には母親が有利になります。
学童期に入ってくると、徐々に父親に親権が認められる事例も増えてきます。
10歳くらいになると子どもの希望も考慮されるようになり、15歳になると基本的に子ども自身が親権者を選べます。
このように、子どもの年齢も親権の判断に影響します。ただ小さいうちは子どもは親権者を選べないので「どちらの親と住みたい?」などの質問をしないようにしましょう。
不倫と親権の関係について
不倫しても親権者になれる可能性はあります。ただし不倫相手と同居している場合、不倫相手を「お父さん」と呼ばせて実親と一切会わせない場合などには不利になるリスクも高まります。
不倫していて親権を取得したいなら、状況に応じた対処方をとらねばなりません。自己判断せずに弁護士へ相談しましょう。
親権を決めるまでの流れ
親権者を決めるまでの流れは概ね以下のとおりです。
STEP1 裁判外で協議する
まずは親同士が裁判外で話し合い、協議するのが一般的です。
話し合いで合意できれば、離婚届に親権者を記載して提出しましょう。
そうすれば戸籍が書き換わって届け出た方の親を親権者としてもらえます。
STEP2 離婚調停で話し合う
自分たちだけで話し合っても親権者を決められない場合には、離婚調停を申し立てましょう。調停では調停委員が間に入って両者の意見を調整してくれます。
ただし調停はあくまで話し合いなので、どちらかの親が譲らないと解決できません。
双方が親権を譲らない場合、調停は不成立となって終了します。
STEP3 離婚訴訟で決定される
調停も不成立となった場合、親権者の判断は離婚訴訟へと持ち越されます。
どちらかの親が離婚訴訟を提起すると訴訟手続が進められ、最終的に裁判官が判決で親権者を指定します。
その際には上記でご紹介した判断基準によって判断されることとなります。
また離婚訴訟では「調査官」によって親権に関する調査が行われます。
裁判官は調査官調査の結果に大きく影響されるので、調査官がどういった意見を出すかは当事者にとって重大事といえるでしょう。
調査の内容
家庭裁判所調査官による調査内容は、概ね以下のようなものとなります。
- 両親からの聞き取り
- 家庭訪問をして子どもの現状を把握
- 学校や幼稚園への訪問、担当の先生からの聞き取り調査
- 別居親との面会交流場面を観察
親権者になりたいなら、調査官調査に適切に対応しましょう。
親権を取得するためにすべきこと
親権を取得したいなら、以下のような行動をとるようおすすめします。
資料を揃える
まずは自分が親権者としてふさわしいことを示す資料を用意しましょう。
たとえば子どもが小さいときからつけていた養育日記や母子手帳、子どもと一緒に写っている写真や学校・幼稚園との連絡帳、これまでの経緯や今後の養育方針をまとめた陳述書などが有用となるケースが多数です。
何を集めればよいかわからない場合、弁護士までご相談ください。
親権の判断基準を知る
親権者の判断基準を知らないと、適切に対応できません。冒頭で紹介したポイントをもとに、法的な判断基準を押さえましょう。
別居時に子どもと離れない
別居時に子どもと離れると不利になることは既述です。相手に一人で出ていってもらうか、自分が出ていくなら必ず子どもを連れて出ましょう。
子どもと一緒に過ごす時間を作る
裁判所は子どもと一緒に過ごせる親を優先する傾向があります。
生活において、なるべく子どもと一緒に過ごす時間をたくさんつくりましょう。
石川・富山・福井で弁護活動をする金沢のあさひ法律事務所では離婚に悩む方々のサポートに力を入れて取り組んでいます。親権争いにお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
石川県(金沢市・小松市・七尾市・白山市・野々市市など)をはじめ、富山県・福井県の離婚や慰謝料に関するご相談に幅広く対応しています。
これまで多くの方のお話を伺い、それぞれの事情に合わせた解決を一緒に考えてきました。つらい気持ちを抱えたままにならないよう、気軽に話せる場所としてお役に立てればと思っています。
初回相談は無料、事前予約で夜間や休日の対応も可能です。相談内容は厳守し、ご不安な気持ちに寄り添いながら、納得のいく解決を一緒に目指します。
※初回無料相談は、事務所で面談して相談する場合に限らせていただいております。電話での初回無料相談は行っておりませんので、ご注意をお願いいたします。
30代女性のための離婚をする場合に考えておくべきポイント
30代女性が離婚する場合、他の年代の方や男性とは異なるさまざまな点に注意しなければ後悔してしまう可能性もあります。
30代女性でとりわけ問題になりやすいのが、子どもや財産分与、慰謝料などです。
この記事では30代前後の女性の方が離婚する際に気をつけておきたいことを弁護士がお伝えします。
離婚を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
30代女性でよくある離婚原因
30代の女性はどういった理由で離婚を決意するケースが多いのでしょうか?
裁判所の司法統計によると、毎年「離婚調停」の申立理由として男女ともにもっとも多いのが「性格の不一致」です。考え方やライフスタイル、物事の捉え方など考え方が合わないためストレスが溜まり、離婚する女性が多いことがわかります。
他の理由としては精神的虐待(モラハラ)や暴力(DV)、生活費を渡してくれない、異性関係(不倫)なども多くなっています。
子どもの問題
30代女性が離婚する場合には、子どもの問題への配慮がほぼ必須でしょう。
親が30代の場合、子どもは未成年のケースがほとんどで、乳幼児や学童期、思春期など難しい年頃の場合も少なくありません。
子どもが小さい場合、両親が離婚すると子どもは片方の親としか暮らせないので、寂しい思いをするでしょう。離婚後、面会に関するトラブルが発生するケースも多々あります。
子どもが相応に大きくなっていると経済的に苦労をかける可能性もあり、心配になる方も多数います。
30代女性が離婚するとき、子どもについて相手ときちんと取り決めをしておくべきです。
最低でも以下の3点については相手とよく話し合って合意しておきましょう。
親権者
親権者は、離婚後に子どもを引き取って育てます。
日本では離婚後は単独親権となるため、どちらかの親しか親権者になれず、親権者が決まらなければ協議離婚も調停離婚もできません。
相手もこちらも親権を希望するなら、最終的に裁判所で親権を決めてもらう必要があります。
裁判所が親権者を判断する場合、これまでの養育実績や現状、今後の教育方針や生活スケジュールなどが考慮されます。
まずは相手と話し合って「子どものためにどちらの親が親権者になるのが良いのか」という視点から判断しましょう。
養育費
子どもの親権者になるなら、養育費についての取り決めも重要です。
養育費は基本的に子どもが20歳になるまで請求できますが(成人年齢が引き下げられても養育費の支払い周期は基本的に20歳までと考えられています)、当事者同士の取り決めによって延長してもかまいません。たとえば大学に進学する可能性が高いなら、22歳になった次の3月までなどと定めましょう。
相手が支払いをしないときに備えて、離婚協議書や養育費に関する合意書は公正証書にしておくようおすすめします。
面会交流
離婚後、相手と子どもとの面会交流が問題になるケースも多々あります。
相手から無茶な要求をされて困ってしまうことのないように、離婚前に実現可能な面会交流方法を取り決めておきましょう。
面会交流については標準的に月1回程度ともいわれますが、実際にはお互いの居住場所や子どもと相手との関係性、子供の生活スタイルや年齢などによって適切な頻度や方法が大きく変わってきます。
どういった方法が最適か判断しにくい場合、弁護士までご相談ください。
財産分与
30代女性が離婚後に後悔しないためには「財産分与」も重要です。
30代のご夫婦ではまだ多くの財産が積み上がっていないケースも多いですが、それなりに貯蓄を形成している方もおられるでしょう。
住宅ローン返済中の場合、自宅の財産分与方法をめぐってトラブルになるケースも多々あります。
財産分与の対象
財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻期間中につみたてた資産や生活費のための負債などです。
資産については、以下のようなものが対象となります。
- 現預金
- 社内積立、共済の貯金
- 保険(生命保険や学資保険など、解約返戻金のあるもの)
- 不動産
- 車
- 貴金属や骨董品などの動産類
負債については、生活のために借り入れたカードローンなどは分与対象になる可能性がありますが「マイナスの財産分与」は行いません。
つまり、全体としてマイナスになってしまう場合、相手名義の負債を半分背負わされる心配は不要です。負債はあくまで名義人が自分の責任で返済していきます。
住宅ローンつきの自宅精算方法
30代ご夫婦の場合、住宅ローン返済中の家の財産分与方法が問題となるケースが非常によくあります。
住宅ローンが残っている場合、家の価値から住宅ローンの残債を引いた金額を「家の価値」として財産分与を計算します。
ただし住宅ローンの方が高額で「オーバーローン」になる場合、家の財産分与は行いません。
名義人は離婚後も家を所有してローンを払っていくことになります。
ただ財産分与の対象になるかならないかとは別に、夫婦のどちらが離婚後に家に住むのか、売却して清算するのかなどを取り決めなければなりません。
夫婦のどちらかや実家が頭金を出している場合には、家の評価を行う際に頭金に相当する金額を差し引いて清算する必要もあります。
どちらかが相手の連帯保証人になっている場合、保証人を外す措置が必要な場合もあります。
住宅ローンが残っている場合の財産分与は非常に複雑なので、迷われたら弁護士に相談してベストな選択をしましょう。
相手が不倫した場合
30代の離婚原因では、不倫トラブルも非常に多くなっています。
夫が不倫したら、夫や不倫相手の女性に慰謝料請求ができます。
慰謝料の相場は100~300万円程度と考えましょう。
夫の不倫を証明できれば相手が拒否しても裁判で離婚を認めてもらえます。ただし不倫トラブルが起こったときに有利に離婚するには「不倫の証拠」が必要です。
法律上の不倫を不貞といいますが、不貞を証明するには「配偶者と不倫相手の肉体関係」を立証しなければなりません。
たとえば単なるLINEメッセージだけでは慰謝料請求できない可能性もあるので、事前にしっかり証拠集めをしましょう。
不倫の証拠として特に有効なのは、性交渉をしているときの動画や画像、宿泊したことがわかるLINEやメールのメッセージ、浮気現場を押さえた探偵の調査報告書、配偶者や不倫相手が肉体関係を認めた自認書や音声録音記録などです。
どういった証拠を集めたらいいかわからない方は、お気軽に弁護士までご相談ください。
石川・富山・福井で弁護活動をする金沢のあさひ法律事務所では、30代女性の離婚案件をこれまで多数、解決してまいりました。子どもや財産分与、相手の不倫などにお困りの方がおられましたらお気軽にお問い合わせください。
石川県(金沢市・小松市・七尾市・白山市・野々市市など)をはじめ、富山県・福井県の離婚や慰謝料に関するご相談に幅広く対応しています。
これまで多くの方のお話を伺い、それぞれの事情に合わせた解決を一緒に考えてきました。つらい気持ちを抱えたままにならないよう、気軽に話せる場所としてお役に立てればと思っています。
初回相談は無料、事前予約で夜間や休日の対応も可能です。相談内容は厳守し、ご不安な気持ちに寄り添いながら、納得のいく解決を一緒に目指します。
※初回無料相談は、事務所で面談して相談する場合に限らせていただいております。電話での初回無料相談は行っておりませんので、ご注意をお願いいたします。